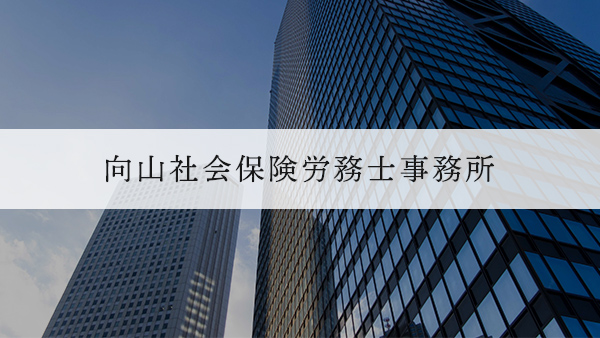社会保険労務士と生成AI
社会保険労務士と生成AI
社会保険労務士の業務についても御多分に漏れず生成AI革命が急速に進行しています。
業務のどの分野に使うかは、専門分野や習熟度により異なりますが、役立ちツールとしてほとんど必須のものになっていることは、ほとんどの社労士の共通認識になっていると思います。
一方で、社労士業務は扱う法律の範囲がかなり幅広く、業務の種類も手続代行、帳簿の作成から労務等相談業務と多岐にわたります。社労士によっては専門領域に特化して活動している方もいらっしゃいますが、私の場合はどの分野も興味深く、早いうちから分野を絞り込むことはせずに依頼のあった業務に一つずつ取り組んでいきたいと考えています。
生成AIの特長
このような社労士が生成AIをどのように活用すればよいのか、私にとって目下の課題の一つになっています。
生成AIはウェブ上の公開情報等をもとに形成された膨大な学習データに基づき、プロンプトによって提示された利用者の要求・タスクに対して言語化した回答例を出してきます。従来のインターネットの検索との最大の違いは、単に情報を提示するだけでなく、ある意味で作業の補助代行機能があります。この特長を業務に生かせるのか、使う場合の注意点は何か、は恐らく社労士一人ひとりのスキルや考え方に左右されるもので、正解というものはないのではないかと思います。
私自身はまだその具体的な内容を述べるだけの経験がありませんが、そのあたりの見極めができるようになることは必要であり、先達の社労士のセミナー等で勉強を始めているところですが、現時点で考えられることを以下に述べたいと思います。
生成AIの得意分野と社労士業務への適用
生成AIの得意分野としては、「利用者のニーズに対するアイデアや視点の提示」、「何らかのアウトプットを要求する利用者への作業補助」、「情報の要約」などが挙げられています。
社労士業務との関係では、法令等の改正があった場合に事業所等関係者に内容を伝える際の資料作り等が最も利用頻度が高いと推測されます。制度改正情報自体は関係行政機関からオンラインで提供されますので、ベースは公知のものですが、これをわかりやすくお伝えすることが社労士の役割であり、情報の受け手によって伝え方を考える必要があるときに、生成AIが頼もしい助っ人になることは間違いないと思います。
しかしながら、近時の生成AIの進歩は目覚ましいものがあり、その活用領域を社労士のコア業務に広げることができるのではないか、ということで研究が進み、一部の取組み事例の社労士関係者への共有も始まっています。
例えば社労士が顧問先事業所に提案する規程等のアウトプットは、多くの場合雛形が行政から提示されていることもあるのですが、それをもとに個別の状況に応じてカスタマイズし、最適と考える内容で納品することが社労士の専門性の見せ所になります。進歩した生成AIは、このカスタマイズの補助機能も担うことができるということです。ここで重要なのは、どういうアウトプットを求めているかを社労士自身が明確にしておくことで、その点が抜けていると「先例に照らして一応妥当と考えられる提案」の領域にとどまってしまいます。このカスタマイズというのはその手法が多くの場合言語化されておらず、まさに専門スキルとして社労士がそれぞれ磨いてきたものだと思いますが、最近はその部分も生成AIに学習させる余地があるのではないか、ということで取組みが始まっていることは個人的には非常に驚きがあります。
また、会話機能があるため、顧問先から受けた相談内容を試みにプロンプトに打ち込み、回答を求めることもできるでしょう。生成AIがベースにしているデータは著作権に抵触しない公知のものに限られているため、現状では社労士が満足する回答が得られることはあまり多くないと思いますが、経験の少ない分野であれば、参考情報として使える可能性はあるかもしれません。
筆者の当面の方針
以上現時点での私見を述べましたが、私自身は今のところ上記で述べたコア業務について生成AIを使うことは控えるつもりです。この時代の社労士にとって重要なことは、①専門知識・スキル、②生成AIを初めとする業務ツールの効果的活用、③法の規定する使命にのっとって業務を遂行する心構えであると言われています。活用方法について指導をして下さる先達の専門レベルに近づいて初めて生成AIの適切な使い方がマスターできるようになるのではないか、と考えています。そうは言っても時代の流れは加速しているように感じます。今求められる社労士像をできるだけ早く体現できるよう、日々精進したいと思います。